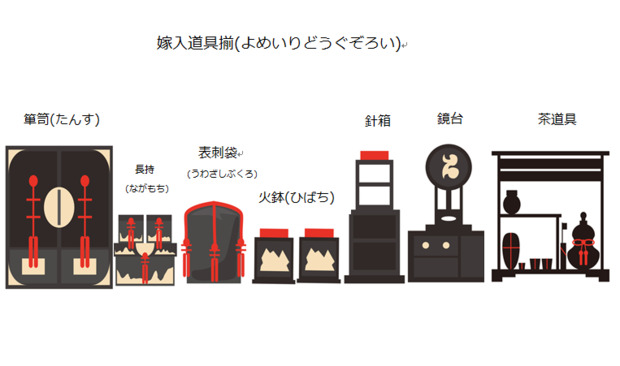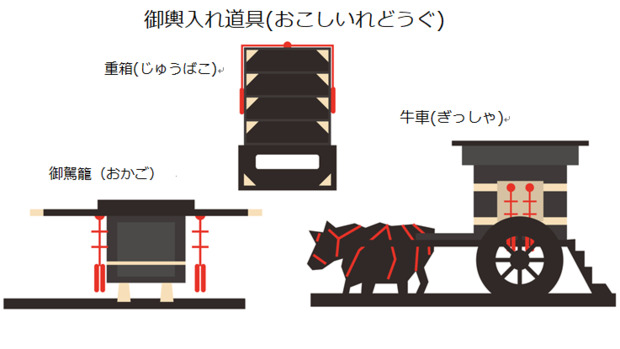毎年ひな祭りには雛人形を飾り、眺めたり写真を撮ったりして楽しみたいですよね。ところが雛人形を飾るときに、並べ方や手順で迷う方は多いようです。ここでは、雛人形の位置や方向などの飾り方・飾る場所など、イラストを交えて分かりやすく紹介します。(この記事は2021年12月時点の情報をもとに作成しています)
本ページはプロモーションが含まれています
雛人形の飾り方や並べ方には決まりがあるの?
雛人形には、男雛と女雛の親王様(しんのうさま)の他、三人官女や五人囃子(ばやし)などの人形があります。五段や七段飾りの場合、随臣(ずいじん)や仕丁(しちょう)という、親王様の護衛やお世話をする雛人形も飾ります。
上段から手袋をはめて扱うのがおすすめ
段飾りの場合、下の段から飾ると上段を飾るときに下の人形や道具を倒してしまう恐れがあります。雛人形を飾る際は、屏風(びょうぶ)や三宝(さんぽう)・ぼんぼりなど、上段の奥に配置するものから順に飾るようにしましょう。人形の顔や道具が汚れるのを防ぐため、布製の手袋をはめて扱うと安心です。
雛人形の飾り方は?【七段をイラスト解説】
段飾りの場合、雛人形を飾る段や配置が決まっています。七段の階段を組み立てたら、人形や土台の傷みを防ぐため、毛氈(もうせん)という赤い織物を敷いてから人形を飾りましょう。
ここでは、七段飾りの一般的な飾り方をイラスト付きで解説します。
一段目 親王様(男雛・女雛)

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/92ebe35a04120829ef47df428dfb511fdb81acb6/store/limit/620/620/274435032f12e00f87efd5e83823d200495038e480ee8074eb1e73198466/image.jpg
雛壇の最上段は、正面から見て左に男雛(おびな)、右に女雛(めびな)を配置する飾り方が一般的です。
男雛は、冠(かんむり)をかぶって笏(しゃく)と太刀(たち)を持ちます。女雛は十二単(じゅうにひとえ)を着て、桧扇(ひおうぎ)を持つ姿のものがほとんどでしょう。