保育士・子育てアドバイザーとして活躍する河西景翔先生の連載第15弾。今回は子どもの「噛みつき」に関してのお悩みを解決してくださいました。子どもが家族だけではなくお友達や保育園の先生に噛みつくと、やめさせなければと思う方がほとんどでしょう。叱って良いのか、噛みつきの背景や対応策はあるのかなどを保育のプロが解説します。
本ページはプロモーションが含まれています

河西先生
今回は、子育てに悩むママの悩みに答えていきます。
ぜひ皆様のお悩みにあわせて、参考にしてください。
保育士・子育てアドバイザーとして活躍する河西景翔先生の連載第15弾。今回は子どもの「噛みつき」に関してのお悩みを解決してくださいました。子どもが家族だけではなくお友達や保育園の先生に噛みつくと、やめさせなければと思う方がほとんどでしょう。叱って良いのか、噛みつきの背景や対応策はあるのかなどを保育のプロが解説します。
本ページはプロモーションが含まれています

河西先生
今回は、子育てに悩むママの悩みに答えていきます。
ぜひ皆様のお悩みにあわせて、参考にしてください。
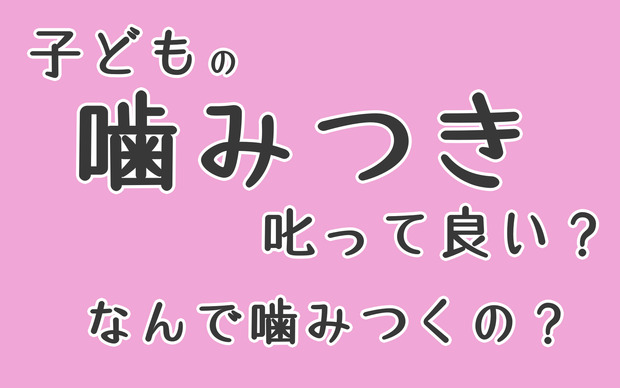
引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/4af625eb48efae0b368b8cf800a1a946acec6596/store/limit/620/620/091d791f3310f10614db2def8053afa66123a9fea319c8ecab4894de068e/image.jpg
1歳2ヶ月の子どもがいます。子どもが家族だけにではなく、お友達や祖父母にも噛みついて困っています。
できるだけ優しく叱ったり注意したりしてみるのですが、繰り返し噛みついてきます。どうしたら良いでしょうか。

河西先生
1歳前後によく見られる噛みつき。
私も1歳児クラスを担当していたとき、よくこの光景を目の当たりにしました。今回は噛みつきの原因や対応を解説します。

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/1d01eabdfc4582e7d33db42dca0932e941b868a5/store/limit/620/620/1c97ac1ba89efc6e6beaa23c53def492b71f6d3242111548c788957c0a92/image.jpg
子どもの噛みつきの背景にあるのは「自我」です。
自我に関しては、イヤイヤ期の子どもたちの心理と似たものがあります。噛みつきは子どもの成長のひとつなので、完全にやめさせることは不可能かもしれません。しかし、噛みつきを減らすことは可能です。
下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説#6】イヤイヤ期のイライラを解決!やってはいけないことは?…一般的に、自分(子ども)の行動を認められると、噛みつきが少なくなると言われています。
たとえば、欲しい物が取れなくて泣いて訴えているときに「取れなかったね。悔しいね」と共感してあげましょう。また、上手にちぎれなかった紙をちぎれたら「上手にできたね!すごいね!」と、紙をちぎれたことを認めてあげましょう。すると、子どもは「この人は、自分の気持を理解してくれる人なんだ!」と承認します。
子どもの自我を認めてあげる大切さを大人が気付かないと、「わかってくれない」という不信感から噛みついたり手を出したりという行動が現れます。まずは、行動をじっくり観察して、子どもの気付きに共感することが大切です。
噛みつきがあると「だめ!」「いけない!」と大きな声で叱ってしまいがちですよね。実は私もそうでした。しかし、その叱りは大人主導の考え方でしかありません。子どもの発達の理解と、噛みつきを減らす空間作りが大切です。
たとえば、おもちゃがひとつしかない場所に、子どもがふたり居たらどうなるでしょうか。「貸して」「いいよ」が理解できる年齢であれば、言葉で表現したり、我慢したりすることができます。しかし、1歳前後でそれができると思いますか?「だめ!」だけで行動を抑えることができるでしょうか。
答えは「NO」でしょう。
まずは大人が先回りして考えていくのです。「1歳児は、ひとりで遊びを楽しむ」という発達段階を知り、噛みつきの原因となるおもちゃを出さないことで、トラブルを回避することができます。

河西先生
保育園では噛みつきを回避するために、子ども同士の遊びが重ならない工夫をしたりおもちゃをたくさん用意したりして、トラブルが起きない環境を作っています。

引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/9e8bef4975b464689bc197901acf79e2da77d1e7/store/limit/620/620/69d17122e2f1f9391d391b6864d6c62248c63b61135493279ad9cf59c739/image.jpg
「噛みつき」は年齢によってもその意味が異なると言われています。今回お話した内容は、主に1歳を過ぎたあたりから見られる、言葉が出ないゆえの噛みつきです。
0歳児でも「噛みつき」は見られます。しかし、0歳児の噛みつきは、親やきょうだいとの楽しいコミュニケーションだと勘違いしているケースも少なくありません。それが癖になって噛みつくということも多いようです。
赤ちゃんは一つひとつの行動がかわいらしいので、すべてにおいて許してしまいがちですよね。しかし、それがかえってトラブルの原因になることもあります。家庭の中で「して良いこと」「してはいけないこと」をしっかりと決めておくことが大切でしょう。

河西先生
今回は、「噛みつき」をテーマにお答えさせていただきました。
子どもの行動には多くの意味が隠されています。その背景を知ることで、トラブルを回避することができますし、子どもを叱るという行動が少なくなります。
大人も子どもも叱られるよりもほめられたほうが嬉しいですよね。子どもの「今」に気付き、楽しい育児ができることを心より願っております。
※この記事は2020年6月時点の情報をもとに作成しています。
YouTubeのままのてチャンネルでは、専門家の先生による育児に関するお役立ち情報を配信しています。河西先生の動画も好評配信中ですよ。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いたします。
下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士お悩み解決】スマホが手放せない!子どもに動画やアプリを見せ続けて大丈夫? 河西景翔#14下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【年齢別】保育士のおすすめ遊びアイテムはコレ!0.1.2歳の遊び方を解説!おうち時間を楽しもう 河西景翔#13下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説】自粛中のママの悩みにアドバイス! 子どもにとって大切なこととは? 河西景翔#12下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説】おうち遊びの悩みを解決!1.2歳の子どもの遊び!プロは保育園でどう接してる? 河西景翔#11下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説】妊娠中のママの出産準備!子育てグッズ・心の持ち方・赤ちゃんとの関わり方を紹介! 河西景翔#10下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説】赤ちゃんと家遊び!生後0ヶ月~12ヶ月の発達に合った遊びとは?河西景翔#9下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説#8】非認知能力とは?世界が注目している理由&子どもの力を伸ばす方法!下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説#7】プロが教える自己肯定感を育む2ステップ!自己肯定感とはどんな力?下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説#6】イヤイヤ期のイライラを解決!やってはいけないことは?プロの接し方を伝授!下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【実録】コロナウイルスで休校!保育士・保護者の現状・生の声は?河西景翔先生コラム#5下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説#4】仕事と育児の両立が不安なママ&パパへのアドバイス!慣らし保育までにできること:河西景翔先生下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士が解説#3】慣らし保育の不安を解決!親子でできる入園に向けての心の準備!下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説!#2】パパの育児参加「イクメン」を徹底解説!男性の育児参画は本当に必要?下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
【保育士解説】保育園選び・見学の疑問を解決!希望の園に入園するには?河西景翔Vol.1
引用元:https://cdn.mamanoko.jp/attachments/c93589f467b2db692684949f4a4f2759e933b9e6/store/limit/620/620/89175c4a513c9f7cb56feadd126ab349401005a4e89355f0a90fd53e9e11/image.jpg
保育士・子育てアドバイザー。
小学生の頃から保育士を目指し、中学から保育園でのボランティア活動を通して、日本音楽学校に入学し、保育士・幼稚園の資格を取得。
「子育て中のママやパパと、共に悩みながら最良の道を切り開く」を念頭において、日々奮闘中。
下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
記事掲載元で確認するままのてのTwitter・Instagramをフォローすると、最新マンガの更新情報をご確認いただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。
下記は外部サイトのためスタンプの獲得はできません。
記事掲載元で確認する